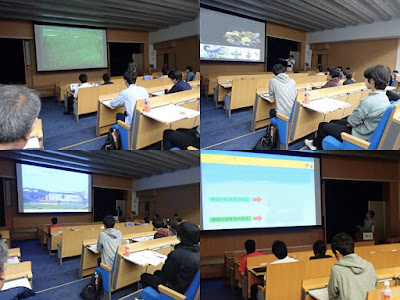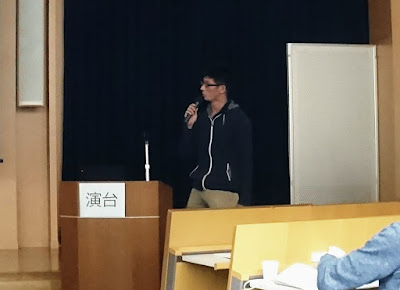東京大学大気海洋研究所 (千葉県柏の葉キャンパス)にて、第二回目の日本甲殻類学会・日本貝類学会合同シンポジウムが開催されました。2つの学会の歴史的合同シンポジウムと言えます。
—————————————————
日本甲殻類学会 ・ 日本貝類学会 共催シンポジウム
「捕食・被食と殻の役割」
Joint Symposium by Carcinological Socity of Japan and Malacological Society of Japan
Crustaceans and Molluscs: Role of Shells and Prey-Predator Relationship
—————————————————
http://csj-symposia-2017.webnode.com/accommodation/
2017年10月6日(金) 東京大学 柏キャンパス 大気海洋研究所 講堂
コンビナー 狩野泰則(東京大学 大気海洋研究所)
実行委員
狩野泰則・猿渡敏郎・大土直哉・中野智之・福森啓晶・高野剛史・矢萩拓也
—————————————————
ごあいさつ
日本甲殻類学会と日本貝類学会は、それぞれ甲殻類および軟体動物の生物学を扱う学会として、ともに長い歴史があります。日本とその周辺域は、甲殻類および軟体動物の種多様性は非常に高く、海洋、陸水、陸上の生態系における重要な位置を占めており、古くからさかんに研究が行われています。またそうした生態系における甲殻類と軟体動物の関係は多種多様で、共生関係、寄生、捕食・被食関係、競争関係など、さまざまです。近年のこうした分類群間の研究によって、非常に興味深い、場合によってはわれわれの想像を超えた面白い現象が発見されています。 こうしたことに鑑み、日本甲殻類学会と日本貝類学会は合同でシンポジウムを開催することとなりました。
第一回目は、2017年4月15日に和歌山県の白浜町で開催され、海外からの3名の招待講演者を含む国際シンポジウムとして、日本貝類学会の大会内で行われました。シンポジウムのメインテーマは「共生、寄生関係に関する進化生物学」で、150名あまりの参加者がありました。
今回、東京大学大気海洋研究所で、日本甲殻類学会大会の開催前日に、第二回目の合同シンポジウムが開催されることとなりました。今回のメインテーマは「捕食・被食と殻の役割」で、貝類・甲殻類間の捕食と被食、あるいはそれに関わる形態進化、または殻を利用した被食回避についてを主たる内容にしたもので、新進気鋭の研究者による最前線の研究内容が発表されます。
日本甲殻類学会会長 朝倉彰
日本貝類学会会長 大越健嗣
—————————————————
シンポジウム趣旨紹介
狩野泰則 (東京大学 大気海洋研究所)
入江貴博(東京大学 大気海洋研究所)
誘導防御:いまさら訊けない蟹と貝のカンケイ
藤原慎一 (名古屋大学博物館)
カニのハサミのかたちと使い方の関係~形態から見積もるハサミの破壊力と壊されにくさ
加賀谷勝史(京都大学 白眉センター・瀬戸臨海実験所)
シャコの殻割り行動の制御機構
石川牧子 (ヤマザキ学園大学)
太古の攻防を垣間見る:生痕から見る貝・ヤドカリへの捕食圧
早川 淳*・大土直哉(東京大学 大気海洋研究所)
大型甲殻類および肉食性巻貝類によるサザエの捕食とその痕跡
中山 凌*・中野智之(京都大学 瀬戸臨海実験所)
捕食回避から見るカサガイの巻貝への付着行動
許 晃(東京大学 生物科学専攻)
イソダニ類の摂餌生態と貝形虫の捕食痕
角井敬知 (北海道大学 理学研究院)
巻貝の殻を背負って生きるタナイス
遊佐陽一 (奈良女子大学 理学研究科)
寄生性フジツボ・トサカエボシのアグレッシブな摂食
AKI, Inomata(現代美術家)
ヤドカリの宿貝替え行動を用いたアート作品の制作
—————————————————
発表された瀬戸臨海実験所の中山くん、中野先生、加賀谷先生、そして白浜水族館でもコラボされたAKI INOMATA さん、ご苦労さまでした!