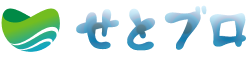過去。過去。過去。
過去とは何だろう。
かつて住んでいた街を訪れ、一つ一つ、いつか見た風景を眺める度に、あの頃がセピア色に蘇る。平原に潜む巨大な怪物が重い鎌首をもたげるように、過去は私の中にふいに現れる。私の心を、冬の北方の色もない湿原に佇ませるように、深く、暗く、冷たいところに沈めていく。
また私はこの街を訪れてしまった。紀伊半島の南に位置する海沿いの街。私がかつて住んでいた街。夕暮れ時の海岸。あの時と同じように広い砂浜を裸足で歩いている。銀色の波が手招きをする。潮風が私の長いスカートを揺らして去っていく。磯の香り。輝く水面。海鳥の鳴く声。すべてが優しいものであったはずだった。だけれど。今の私はこの街に来る度に暗い不安に襲われる。何かを忘れている。それが思い出せない。いや、多分、思い出したくないのだ。けれども私は、何度もこの街を訪れてしまう。あのひどく揺れる電車に乗って。また私はこの街を訪れてしまった。
「海には何かが潜んでいる」
誰だったかそんなことを言っていた。
太陽はもう半分が水平線に浸かり、反対側の空は紺色のアコーディオンカーテンを広げたように夜が広がっている。辺りは薄暗く、けれども夕日側の水面は宝石箱をひっくり返したようにキラキラと光りを反射していた。ふいに夜の闇に妖艶に光る蛍の情景が目に浮かんだ。背筋が冷たくなる。私は蛍が怖かった。蛍という虫が怖いのではない。あの闇夜に艶めかしく光っては消えていくあの風景が怖いのだ。そういう意味では、誰もいない夜道にぽつぽつと等間隔で光っている街灯や、クリスマスの時期に、誰が設置したのかもわからない、路地の隅の方で光っているイルミネーションなんかも怖かった。でもそれがなぜかはわからなかった。
まだ宿に帰るには早すぎる。久しぶりにあの港に行ってみようか。この街に住んでいた頃、私はとある臨海実験所の学生だった。そこは研究に集中するには絶好の場であったが、当時の私は休日になるといささか手持無沙汰になっていて、女ながら魚釣りにどっぷりとハマってしまったのは仕方のないことだった。休日の院生部屋で小説を読んでいる時に、釣好きの先生から、「こんなに天気が良いのだから、釣りにでも行かないか」と声を掛けられたのが始まりだった。その先生と頻繁に通っていた港である。この街を去って、何度かここに帰ってきたが、その港に足を運ぶのは今回が初めてだった。
懐かしい。本当に楽しかった。防波堤の先端まで歩いてみる。少し風が強くなってきた。スカートを押さえる。今日は釣り人はいないみたい。先端には大きなテトラが折り重なっていて、イカ釣りの人はよくここから投げている。水面を覗く。ふいに既視感を覚えた。耳鳴りがする。そう。私は前もこうやって恐る恐る水面を覗きこんだ。何があったんだっけ。もう少しなんだけど。
防波堤の上を、もと来た通り戻っていく。もう辺りはかなり暗くなっている。私の目の前に連なる街灯がぽつぽつと点灯した。私から見て一番奥の街灯の下に誰か立っている。あれは………。
「先生…………..?」
その街灯の下の人影は何か口を動かしている。何だろう?何を言っているの?眼を細める。口の動きに集中する。
「海ニハ何カガ潜ンデイル….。」
あぁ、そうだった。私は、あの時…………。
はっとした。きょろきょろと辺りを見渡す。街灯の下には当然ながら誰も立ってなどいなかった。
夏で、お盆が近づいていた時期だった。私と先生はこの港で夜釣りをしていた。夜中の3時くらいだった。先生が水面に眼をやり妙な顔をしている。
「あれは、なんだろうね?」
私も水面に眼をやる。野球ボールほどの丸い緑色の塊が、長い尾を引いてくねくねと水面を泳いでいる。最初は5、6個程度だったのが、気が付けば10、50、100個と増えていった。その光の塊はS字を描きながら泳いだり、互いに円を描きながらくるくる回ったり、水面下に消えては再び現れたりした。そして私は、それは怖いものだと感じつつも、その幻想的な姿に見入ってしまった。まるで、闇夜に舞う妖艶な蛍の光のようだった。そして私は無意識に一つの光の塊に集中していた。その塊はしばらく8の字を描いて泳いでいたが、急に水面下に消え、また上に戻ってきた。そうだ。その時だ。そいつが消えて、再び姿を現した時、それは光の塊なんかではなかった。そう、あれは私のよく知っている…………..。
「……………..——————っ君!!!!!!」
先生の声で現実に引き戻された。先生?なぜそんな怖い顔をしているの?痛い、なぜそんなに強く手を握るの?
後ろを振り向く。そこには暗い水面が広がっていた。私はもう少しのところで海に落ちるところだった。
その翌日、耳を劈く電話の音で目が覚めた。電話は実家からだった。
完
posted by 望月