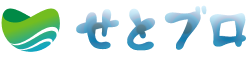僕は当時、バックパッカーとして日本の各地を自転車で旅していた。大学の学部2年生の夏で、高校時代、夢に描いていた大学生活と(当然ではあるが夢のようにはいかない)現実とのギャップに、 半ば惰性的にどこで間違ったのかと生産性のない後悔を6畳の部屋でうんうん言っていた時に思いついたのだった。時は金なりというが、本当に時間がお金になったらどんなに良いかなどとそんなことを考えながらこの狭苦しい部屋で若さと時間にあふれる貴重な大学2年生の夏を潰してはならない、そんな強迫観念じみたものに急き立てられ僕は自転車に乗った。
九州地方の海岸線を走っていた時だった。海の反対側は永遠と林が続いていて、眩みそうになるくらい騒々しく鳴いていた蝉の声が消え、代わりにどこか不安な気持ちにさせる蜩の声がカナカナと夕暮れの空に響いていた。その古い日本家屋が林の間からぬっと現れたのは突然のことだった。重い存在感にしばらくの間茫然としていた。少し躊躇ったが、もう夜も近いということで、今日はここに一晩泊めて貰えるようにお願いすることにした。Tシャツが汗でべったりと肌にくっついて気持ち悪かった。玄関から出てきたのは60歳くらいの女性で、事情を説明すると快く招き入れてくれた。その玄関に足を踏み入れた一瞬、庭に咲き乱れる饅頭沙華が眼に入り、立眩みに似た感覚を覚えた。蚊取り線香の匂いが鼻先を掠め、どこからか風鈴の音がした。
お風呂上りに座敷部屋で団扇を仰ぎながら涼んでいた。横になっているとすぐに寝てしまいそうになる。現実が霞んでいく。この古い木造家屋が放つ独特の匂いが好きだった。天井の木目の模様を眺めながら深呼吸する。向こうの廊下から足音が近づいてきた。襖がさっと開き、先程の女性と同じくらいの年齢の男性が入ってきた。この家の主人であろうか。浴衣を着て両手には日本酒と煙管を持っている。
「旅、してるんだって?」
「はい………..。」
「まぁ、飲みなさい。」
彼はおもむろにその場に座り、酒を勧めた。しばらく無言で飲んでいた。僕は気まずくなって、もぞもぞと足の位置などをやたらと変えていたが、彼の方は薄く笑みを浮かべ気持ちよさそうに飲んでいる。
「夏だし、海も近い。少し昔の話をしよう。君もしばらく海沿いを走るなら気をつけたほうがいい。」
もう外は暗くて何も見えないが、彼の後ろの日本庭園に広がっているはずの饅頭沙華が騒いだ気がして、背筋が冷たくなった。
その臨海実験所は紀伊半島の南にあって、夏には関西の都市圏に住む人々を中心に観光客でにぎわう有名な浜辺の近くに立地している。
私は学生としてその実験所に住んでいたのだが、そのころは夜釣りにはまっていてね、ちょうど今日みたいな真夏日の夕方に、よく実験所近くの海に釣りをしに出かけていたよ。その日は夕焼けが怖くなるほど綺麗でね、釣れる予感がしていた。
まぁ、予感だけで、全然釣れなかったのだけれども。22時くらいだろうか、急に風が止んで水面が鏡みたいになった。風が吹かなくなっただけで、空気が異常に重くなった気がしてね、辺りも気味が悪いほど静かになった。何か眼に見えない布のようなもので辺りを覆われた感じかな。ふと、背中越しに気配を感じたんだ。ザっザって砂浜を歩く音がして。あぁ、実験所のメンバーが様子を見に来たんだな、そう思った。釣れていないから気まずくてね、無視して海に浮かぶ光ウキに集中しているフリなんかしてたよ。だけれどいつまでたっても声を掛けてこない。気のせいかと思って釣りを続けていた。そしたらまた、ザっザっザって砂浜を歩く音がする。なんだ居るんじゃないか。釣れてないのが分かっていて声を掛けないんだな、嫌味な奴め、そう思って振り向いた。そうすると居ないだよね、誰も。確かにあの音は重みのある何かが砂の上を歩いた時の音だった。一回だけなら気のせいで済んだかもしれないのだけれどねぇ。どんなに辺りを探してもやはり私しか居ないんだ。急に気味が悪くなった。それでも引き上げられないのが釣り好きの性でね、せめて一匹だけでもって粘ってしまった。
ごくり。僕は思わず唾を飲み込んだ。日本酒を飲みすぎたせいか、喉が異常に渇いている。煙管から出ていく煙が天井に染み込んで消えていった。夏の夜の日本庭園。風鈴の音がどこからか聞こえてくる。一体どこに吊り下げているのだろう?せっかくお風呂に入れてもらったのに汗を沢山掻いてしまった。暑い。そういえば、窓や襖を空けているのにさっきから全然風が吹いていないじゃないか。
結局、時計の針がてっぺんを過ぎるまで粘ってしまった。もう今日は無理だな、片づけをしようとしてその場に屈んだ。……………そしたらまた聞こえてきたんだ。ザっザっザって。今度は私のすぐ後ろから砂を踏みしめる音がした。私は一瞬凍りついた。光ウキを握りしめながら、震えていた。もう最初の足音がして二時間は経っている。普通の人間がうろうろとただ歩くためにだけに、そんな長時間こんな処に居るはずもない。しかも灯りも持たずに深夜に。だけれども私には振り向く以外の選択肢はなかった。だから思い切って振り向くことにした。額から、嫌な汗が流れていた。その時だった。ああ、ちょうど振り向こうとしたその時だ。私の後頭部のすぐ後ろから鈴の音が聞こえてきたんだ。
‘…………………….チリン……………………’
座敷部屋はもとの沈黙に戻った。体の表面は暑く、不愉快な汗が伝っているのに、体の中は寒さに震えている感覚だった。座敷の隅の方で虫か何かが動いた。思わず日本酒を飲む。粘っこい液体が喉を這うように通って行く。風鈴の音が聞こえる。彼は煙管から煙をゆっくりと吸い込み、吐き出していく。
「それで……….?」
「それだけだよ。」
僕はふぅーと長い息を吐いた。畳の網目に爪を引っ掛け、がりがりと手を持て余す。だいぶ飲みすぎたらしい。頭がぼんやりする。
「君も海辺を夜に通る時は気をつけた方がいい。」
「…………はい。あの、さっきから風鈴ですか?いい音色ですね。」
彼は一瞬驚いた顔をして、すぐににやりと笑った。
「君ね、風も吹いていないのに風鈴が鳴るわけがないだろう…………….」
続
posted by 望月