概要
開講期間
令和8年3月21日(土)14時集合~3月25日(水)正午までに解散(5日間)
開講場所
京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 研究棟1階 共同利用実習室
担当教員
下村 通誉(教授)
中野 智之(准教授)
河村 真理子(講師)
後藤 龍太郎(助教)
山守 瑠奈(助教)
協力教員
田村 実(京都大学理学研究科 教授)
布施 静香(京都大学理学研究科 教授)
倉島 彰(三重大学生物資源学研究科 教授)
対象学年
学部学生(大学院生も可)
受講に必要な要件
- 学生教育研究災害傷害保険(学研災)、またはこれと同等以上の保険への加入
- 学研災付帯賠償保険あるいは学生賠償責任保険、またはこれと同等以上の保険への加入
単位数
2単位相当(授業単位の認定はできませんが、代わりに授業の受講証を発行します)
費用
宿泊費・昼夕食費として約13,000円かかります。(交通費と朝食は各自別途負担)
持参するもの
【必要なもの】
筆記用具一式(野帳、スケッチ用の鉛筆、レポート用紙など)
汚れてよい長袖長ズボン、帽子、タオル(野外実習で使用)、カッパ、防寒具
【あるとよいもの】
ノートパソコン(4台まで実験所で貸出可能)
*洗濯機3台を利用可能。その他の生活用品は宿泊棟のページを参照のこと。
定員数
10名(定員を超えた場合は、所属が重ならないよう配慮した上で、抽選となります)
主な内容
岩礁潮間帯に繁茂する大型藻類(海藻)と、海岸周辺に生育する海浜植物について、その分類と生態を学びます。また、海藻の生育環境や海浜植物の形態的特徴を理解し、それぞれの分類群の海岸環境への適応現象を考えます。
磯観察と標本作製
自然海岸の潮間帯に繁茂する大型の藻類(海藻)について、形態や生態を観察します。観察場所の番所崎は、黒潮の影響を強く受ける岩礁海岸で、大小様々のタイドプールがみられます。現場で海藻の色、形、手触りを観察し、標本として採集します。持ち帰った海藻は図鑑で調べ、同定の基準となる組織切片のスケッチも行います。また、種ごとの押し葉標本を作製します。

海藻の分布調査
タイドプールの大きさ、深さ、海からの距離、標高、日当たり、海藻食のウニ類・アメフラシ類の分布など、海藻の生育には様々な環境が関係しており、またその関係は種ごとに異なります。現場で各種の海藻の同定作業を行い、種ごとの水平・鉛直分布と生育環境について考察し、図表を用いて発表します。

海浜植物の野外観察と標本作製
番所崎周辺では、比較的自然な海浜植物植生を観察することができ、潮下帯では陸上から海中へ適応進化した植物(海草/うみくさ)が繁茂しています。
内陸部に生育する陸上植物と、海浜植物あるいは海草の形態的差異から、海浜や潮間帯・潮下帯への適応的な特徴を理解します。一部の植物を採集して持ち帰り、図鑑で同定して押し葉標本を作製します。

海浜植物の適応現象の観察
海浜植物は、強風、塩分、乾燥、強い日差しなど、過酷な環境に適応した形態的特徴を持ちます。これらの適応現象を観察し、各自で決めたテーマに沿って、より定量的に調査・解析します。生育環境に適した種間あるいは種内形態変異や、海流散布に適した果実・種子の形態など、様々なテーマで発表を行います。
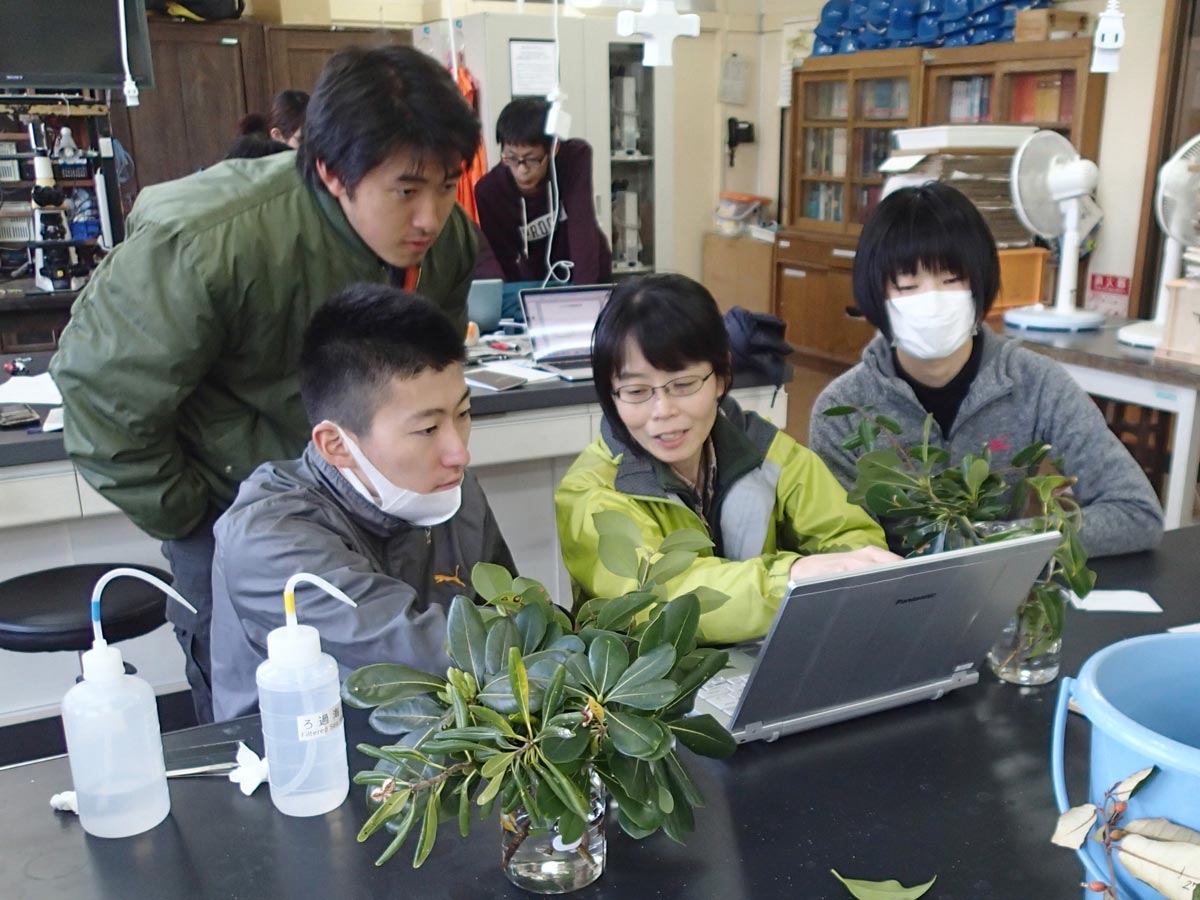
受講のお申込み
申込締切
令和8年1月30日(金)必着
申込方法
オンラインでお申込みください。
受講の可否については、2月上旬頃に受講生・指導教員に電子メールで連絡し、その後教務担当宛に許可書を郵送いたします。
問合せ窓口
後藤 龍太郎(実習担当)
E-mail: goto.ryutaro.8n<at>kyoto-u.ac.jp(<at>を@に変えて送信)
Tel: 0739-42-3515(平日9:00~17:00)
Fax: 0739-42-4518
